 |
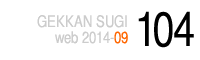 |
|
||||||||||||||||
| チシュウフウ/福岡女学院大学 | ||||||||||||||||
今回のプラグラムに参加させていただいて、本当にありがとうございます。私が大学で「まちづくり、歴史的な街並み、観光まちづくり、地域活性化」を勉強していますが。このような地域住民と交流しながら、地域の良さを再発見する活動ははじめです。たくさんの刺激を受けて、出会い、学びができて、本当に感謝します。論理と実践をうまく生かしながら、バラスをよくとれるように、このようなプラグラムは自分が教室の中で勉強した内容を実際に実践していくことができました。地域再生に直接に貢献できなかったかもしれませんが、これから、「よそもの」「ばがもの」「わかもの」と呼ばれる私たちいが一緒に努力して持続すれば必ずこのプログラムが実現できると信じています。 今度のフィールドワークにもぜひ参加させてください。 |
||||||||||||||||
曺 蓮河 <チョ・ヨナ>/SONY株式会社 |
||||||||||||||||
町づくりは、人が暮らす街を作ることなので、活動の全てのところにどれだけ人間力が必要なのかが分かった。藤原先生の人を巻き込む素晴らしい能力は、インフラや知識ではなく、情熱であることを学んだ。 |
||||||||||||||||
| イ・インソ/韓国産業技術大学 | ||||||||||||||||
始めから問題に関して討論して、問題中心の狭い視覚を持つことより、現地住民たちと村を巡ってみて下浦をより広い観点でみて考えられればいいと思います。今回の機会を通じてデザインというのは外的な美を目指すことだけではなくて、現場で学んだ感情的な表現も重要だと考えました。そして、この二つが一緒になってからこそ、デザイン文化になるだろうと思いました。 プログラムの全てが有意義で、楽しい時間でした。ワークショップのみならず、ホームステイも大切な経験でした。ホームステイを通じて下浦の住民たちと交流ができ、日本の家庭も体験できました。残念なのはグループ活動の時間が短かったことです。もっと長かったら良かったと思います。また、日本語を話せないので沢山の人と交流しなかったのが残念です。しかし、2泊3間沢山の事を学びました。下浦の美しい様子をまた見たいです。次回参加できたら、その時は日本語の勉強も頑張ってもっと積極的に参加したいと思います。 |
||||||||||||||||
李 相敬<イ・サンギョン>/韓国産業技術大学 |
||||||||||||||||
| 非常に有意義で楽しい時間で、忘れられない経験になりました 。 ただ、地域の方々と触れ合える時間がもうちょっと欲しかったですね。 心残りはそれぐらいかな。 |
||||||||||||||||
| 金 智善<キム・ジソン>/韓国産業技術大学 | ||||||||||||||||
2泊3日間の短いワークショップだったが、下浦の発展のために新しい人が集まって、プログラムを進行するということは有意義だと思います。韓国人として言語疎通が円滑にならなかったので、あまり積極的に参加できなかったのが残念です。 |
||||||||||||||||
チェ・ヨンヒ/韓国産業技術大学 |
||||||||||||||||
初めて参加してみたワークショップでしたが、とても興味深かったし、いい人たちと交流ができ、幸せでした。 |
||||||||||||||||
| パク・ジンソル/韓国産業技術大学 | ||||||||||||||||
このように文章を書きながら、前の事を思いおこすと大切な思い出になったと思う。プログラムの構成は良かったが、時間が短かったのが少し残念である。もっと、沢山の体験をしたかった。プログラムの一つ一つが結局下浦の改善を目指しているので、それぞれのプログラムを行って、他のプログラムと結合するかたちで進化して行ってもいいと思う。 |
||||||||||||||||
| 五十嵐浩司(いがらしこうじ)/パワープレイス株式会社 | ||||||||||||||||
今回参加できることになって、最初はどういう立場でワークしていこうか迷いはあった。でも実際FWが始まってみると、そんなことあまり気にせず、というかする必要もないなと思えた。参加者がそれぞれに自主的な意思を持って参加しているので、熱い人達が多く実際熱かった(笑)町の人々のニュートラルな姿勢もとてもよくて、歓迎してくれるありがたさと、普通に接してくれるありがたさがあった。 |
||||||||||||||||
| 千代田健一(ちよだけんいち)/パワープレイス株式会社 | ||||||||||||||||
今回は初めての土地で、初回訪問ということだったので、まちの人々と深く語り合う時間が殆ど無かったと言っていい。九州大学藤原惠洋研究室としての地方都市再生のための方策研究として見た場合、若者の意識を地方都市や過疎地域に向けるきっかけとしてはとても優れたプログラムだと思うし、いつかはこの経験を積んだ者が活躍社会人として実際赴いたまちに寄与したり、他の地域において実を結ぶこともあると思います。 |
||||||||||||||||
| 大津 由理(おおつゆり)/福岡女学院大学 | ||||||||||||||||
無理を言って途中から2日間参加させていただきました。 |
||||||||||||||||
| 長谷川千紘 (はせがわちひろ)/愛知淑徳大学 | ||||||||||||||||
今回、初めてフィールドワークというものに参加して、視野が広がりました。愛知から一人参加して、誰も知り合いがいないという状況の中、うまくやっていけるかすごく心配でしたが、みなさん本当に優しくて、参加して良かったと実感しました。民泊先のお父さんやお母さんにもとても良くしていただき、田舎の祖母の家に帰省しているような感覚でした。人生のなかで無人島に行くことなどきっとないですが、無人島に行くという貴重な体験ができたし、夜寝ていて足の上に蜘蛛が乗ってくるなんて体験もできたし、下浦で過ごした時間は非日常という感じがして、日々の学生生活の中では体験できないことづくしで、とても楽しかったです。日本にはこんな素敵なまちが残っていたんだと実感しました。そして、何よりも自分の地元と下浦が繋がっていて、本当に驚きました。下浦の石工の職人さんたちが岡崎に石工のまちをつくり、今では下浦の石工の職人さんたちが岡崎へ修業に来たりと、私が下浦へ行ったのには意味があったんだと(勝手に)思いました。笑 これも何かの縁だと思うので、岡崎の発展の過程をたどりながら、これからも下浦のまちの発展をお手伝いできたらと思います。このフィールドワークを企画してくださった藤原先生をはじめ、研究室スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。 |
||||||||||||||||
| 内田 亮 (うちだ あきら)/パワープレイス株式会社 | ||||||||||||||||
九州には旅行で何度か訪れたことがあるのですが、天草には行ったことがなかったので是非行ってみよう、という動機も半分くらいある中での今回のフィールドワーク参加でしたが、思い掛けず様々なモノ(想い、情熱、希望、期待、反省など)を持ち替える旅となりました。 |
||||||||||||||||
| 木村敏之(きむらとしゆき)/ソニー株式会社 | ||||||||||||||||
少し残念だったのが、折角海外から参加してくれた韓国の学生さん達との交流やサポートが十分ではなかったように感じられたことです。Aグループは各個人での発表を行っていましたが、彼女達の経験という点では成果物までグループで導けるような流れの方が良かったかもしれません。私自身、学生時代に韓国でWSに参加し言葉が通じないながらのコミュニケーションが大きな糧になった経験があったので。 |
||||||||||||||||
| 小野裕幸/(株)こどもデザイン研究所 | ||||||||||||||||
第1回目であり、これから時間をかけて掘り下げてみたいと考えています。 |
||||||||||||||||
| 金子賀寿彦/ | ||||||||||||||||
前年度から計画を進めていた下浦フィールドワーク事業を無事行う事が出来ました。1年目ということで、全てが初めてでしたが、大きな問題もなくスムーズに3日間を終えました。 |
||||||||||||||||
| 佐々木安子/ | ||||||||||||||||
石工・世界遺産・グラバー邸・・・ 一つ一つの言葉はどれも知ってはいたが、これらすべてが「下浦」とつながりがある事を学んだのは、初めて参加した5月28日のコミュニティセンターの会議の席だった。 フィードワーク当日は外回り的なことでしか参加できなかったが、その中でも多くのことに気付いた。 |
||||||||||||||||
| 渡邊英人/ | ||||||||||||||||
皆さんは「グローカル」という言葉をご存じだろうか。 予想外での学びの一つはゴミ対策。これは次回につなげる課題に気付けた。資源ゴミの分別についてオリエンテーションは不可欠。 |
||||||||||||||||
| 冨安 英猛/下浦調査研究事業実行委員会 | ||||||||||||||||
下浦フィールドワークの最中に、藤原先生から「江戸城御用達の石山を守る」という日本経済新聞の記事をみせていただきました。 |
||||||||||||||||
| 張慶彬(ジャン・ギョンビン)/藤原研究室博士1年 | ||||||||||||||||
私の故郷は韓国の釜山です。軍事独裁による黒い社会の背景や工業化によって急変する都市の中で生まれました。その後、私は韓国の民主化や脱工業化を経験しながら失った釜山の魅力や共同体に関して考えることになりました。韓国は2000年前後から「まちづくり」という概念を取り入れ、実施しています。しかし、従来住民参与の経験が少なった韓国では、住民によるまちづくりより、行政によるまちづくりが頻繁に行われ続けています。そこで私は、「まちづくりとは何か?」という疑問を持ち、アジアで初めて「まちづくり」という概念を使い始めた日本への留学を決心しました。 一. 「下浦で会いましょう」 二. 「下浦を学ぼう」 三. 「下浦を育てよう。」 |
||||||||||||||||
| 張榮珉(ジャン・ヨンミン)/藤原研究室研究生 | ||||||||||||||||
2014年7月25日~27日、最初ので行われた天草下浦のフィールドワークを参加する前には藤原研究室に数多くのフィールドワークの一つとだけ考えていた。どのように進められるのかどのような準備をしなければならないのか下浦はどのような町なのかを把握しないまま出発をするようになりましたし、多彩な専門分野のデザイナーたち、学生たち、先生など多くの人が一緒に参加するフィールドワークははじめてだったのに出発しはじめてから全体的な雰囲気を把握して精神がなかったのが事実だ。現場に到着しても、やっぱり不足した日本語の実力によって進行過程をまともに把握していなければ、私が果たして役に立つことができるかを考えていた。しかし、様々なプログラムが進行してチームを分けて活動をするようになり、今回のフィールドワークを進める理由及び下浦に対する全体的な雰囲気、目標を自然に知り合うようになったし、私も一員として私の考え方及び私にできる分野についてできるように努力するようになった。 二番目の日行われたA、B、C、D、E、F、Gでチームを分けて活動をしながらは一つのテーマについて、チーム別に集中度をもって悩みできるという部分でいいと思っていたが、初めて行われたフィールドワークだったため、問題点を把握して代案を提示する上ではやはり時間が不足したと思う。しかし、このような過程たちは初めて行われるフィールドワークであるため、必ず必要な過程だと考えをして回収が繰り返すほど同じ部分に限って悩みをするのではなく行われた過程での問題点を正確に把握して2番目に行われるフィールドワークでは問題点把握と代案提示する過程が、さらに発展されなければならないだろう。私はCチームで活動をしたがCチームでは無人島をテーマに進められた。Cチームに集まった人たちは無人島で出発する前にまず服装から点検をした。無人島であるだけに、蛇が出る可能性もある、暑い天気なのにもかかわらず、無人島であるため、陰がなく、虫もたくさんある可能性があったために腕が長いTシャツやタオル、帽子、長いズボン、運動靴は基本的に必要した。そして出発する前に会議を簡単にし、無人島に到着して周辺を体験して経験しながら個人的に思ったことをメモ紙に作成して、長所、短所に分けて無人島を通ってきた後に総合することにした。Cチームのチーム員たちが'無人島'いう名前自体だけでも興味と期待を持っていたし、私も初めて行ってみている無人島に大きな期待をして無人島で出発することになる。無人島に行く過程からが相当興味深い。出発する上では船に乗って入るが、彼の全景が最高だ。青い空と海の色、遠くから見える青い無人島風景がとても美しい無人島に行く道は期待感を高めた。、無人島を振り返り、無人島の形態によって泳ぐことができる安全な場所及び無人島だが、陰が存在するところ、特に石が多く存在して生物のヒトデ、貝、などがたくさんあるなど、やっぱり一番良いメリットは'自然'の直接的な体験というものだった。、無人島を経験してきては各チーム毎に発表することになるが誰一つ漏れなく一生懸命やったし、チームメンバーの中でもそれぞれのできる分野があったために、各自の役割を務め、チーム員たちはプロジェクトを進行した。私自身はやっぱり日本語の直接的なコミュニケーションが不可能だったため、その場で努力できる部分を見いだそうとした。しかし、発表をしてやや物足りない部分があると思ったのに無人島の全体的な把握は可能だったが、代案を提示する部分において、非常に不足し、代案を提示する部分が不足したために発表をした内容が'無人島では、自然体験が可能である'に止まったということに相当したのは残念だ。当時、現場を経験した私の考えは無人島に到着をして無人島を振り返り、無人島は本当に'無人島'ということだ。名前自体だけでも理解できるが、現場を経験してみたら、もっと悩んでいるしたのは果たして'無人島'で'何'を'どう'発展させることができるか、ということだった。当然、この問題を持って無人島を調査しに行ったのだが、現場を目で経験してみたら、困っていたのが事実だった。今回のフィールドワークでは無人島体験を通じて無人島の事実的な雰囲気や地形図の把握が可能であり、単純に考えて周辺に海があって自然があるので、遊泳できるということと自然的な体験な釣りや木、砂、石などを利用して自然を体験することができるプログラムを作ることぐらいだが、これをどのように観光化させて単純に考えられることだけでなく無人島でのみ可能なもっと特別な代案を提案することだけじゃなくこの代案の中で現実的に可能なものを選択し、事例としてコンピューターの技術的な面を利用してシミュレーションしてみるのが次の進行されるフィールドワークでの課題だと思う。同時に自然を最大限傷つけず、観光化できる方法の部分も落としてはならないのだ。多様な分野における人たちが参加して意見を述べ、代案を一緒に提示するという部分はかなりの効果をもたらす。一つの視線で考えるのではなく様々な技術を持った人々が様々な視線で眺めながら一つになって一つのプロジェクトを実行するということは考えなかった相当な効果を招き、彼に対する結果物もすごいということを改めて直感することができた。やっぱりプロジェクトを実行する原動力は'協力'だと思った。今度行われるフィールドワークでもさらに多様な分野における学生、デザイナーなどの人々が参加してプロジェクトを進めることができるようになることを期待する。また一つ、忘れられない部分がありますが、下浦の住民のみなさんだ。下浦の地域住民たちの親切さに感動をしたのだ。天気も暑かったから体力が足りないもできた状況だったが、美味しい食べ物を提供してくださっては考えなかった小さな部分まで丁寧に配慮してくださったおかげで無事にフィールドワークを終えることができたと思う。とてもとても感謝した心に'監査'の心をどう表現したらいいのか分からない。留学生活をしながらの今回のフィールドワークはとてもいい経験で、体験だった。私がこのプロジェクトの一員として参加をして活動をしたこと自体だけでも光栄だと思うけど、今回のフィールドワークでの残念さなら、当然足りない日本語の実力で全体的な雰囲気把握をし精神なしにた自分自身を振り返って見るようになり、私が助けなりうる部分において自らの役割を果たせなかったという部分が一番残念な思いが残る。これから先あるフィールドワークも当然参加することであり、心残りを後にして今度は私ができる部分を明確に把握し、より積極的に取り組んでみたい。 |
||||||||||||||||
| タカクラタカコ/藤原研究室 | ||||||||||||||||
天草下浦の熱い熱い夏 Shimoura Beat 下浦の音を集めた一つの映像が出来上がった。 今年で四回目となった天草フィールドワーク。毎年、新しい出会いがあり、新しい発見がある。 熱い夏が特別な日になるんじゃなくて、この熱さを日常にも持って色々なことに取り組みたい。 下浦フィールドワークを支えてくれた地域の皆様、藤原惠洋先生はじめ今回出会った皆様、参加出来なかったけど熱い気持ちを送ってくれた皆様に感謝の気持ちを込めて。 |
||||||||||||||||
| 中村緑/ | ||||||||||||||||
「3日間天草の下浦でフィールドワークがあるよ、参加してみる?」 今回、二泊三日という短期間であったが、毎日毎日、一瞬一瞬が出会いの連続だった。町を歩いたり、無人島に行ったりと様々なものを見て、体験した中で、特に地元の方々との「会話」が心に残っている。それは宴会の席のようにセッティングされた場面ではもちろんのこと、町を歩きながらぽつりぽつりと生まれる会話、すれ違う時の温かい声かけなどだ。とりわけ2日目の夜の会話が印象的だった。地元の方々とのバーベキューにおいて石工の方と話す機会があり、仕事への情熱と信念、下浦の現状を見つめる冷静な目、下浦の石工の歴史を語る姿が忘れられない。観光パンフレットや情報サイトからは得られない声を聞くこと、知ることはとても新鮮だった。 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
藤原 風人/駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部4年生 |
||||||||||||||||
2014年7月25日から2泊3日という行程で開催された下浦フィールドワークでの体験は、これまでの私の中にあった世界観を大きく変えるきっかけになったと言っても過言ではない。昨年の9月から、大学の交換留学生として1年間という期間でアメリカはロサンゼルスにあるカリフォルニア州立大学に国際社会学を学びに行っていた。現地では主に、アジアを中心とする現在活性化している地域の歴史的、文化的、宗教的背景がどのようにグローバリゼーションに伴う変化に影響しているのかという点に着眼し、研究を進めていた。社会全体を中心として考えるマクロ視点からの考察方法である。 今回九州大学藤原研究室を中心として行われた天草・下浦フィールドワークでは、よりミクロな視点、つまり細かい視点で考察し、新たなアイディアを発想し、そこに眠っている原石を見つけて、それを磨きあげ、再度地域全体を盛り上げられないかという事が論点と中心になった。その地域に住む人々が今までどのような生活を営み、どのような歴史を持ち、どのような考えを持ってきたのか、社会全体という大きな枠組から捉えるのではなく、個々人という小さな枠組みから捉える事が重要視される。これは、交換留学期間中に学んだ事や、これまで国際社会学という学問の中で学んできた事とは異なり、とても新しい体験となった。はじめは地域の方々へのヒアリングや、共同作業に若干の戸惑いを覚える事もあったが、それは間もなく解消される事となった。フィールドワークの参加者のみが調査を行うのではなく、地域の方々との交流を通し、さらに共同で行う事でお互いの距離感を縮める事が出来たのだ。学部生、大学院生、研究生、デザイナーとして活躍されている社会人の方々、更には海外からの来訪者といったバラエティ豊かな参加者層も、様々な視点や観点からアイディアを出し、それを共有するという一連の作業をユニークに行うトリガーにもなっていたのだ。調査内容としては、学術的に歴史的、文化的背景をもとに難しく調査を行うのではなく、地域の方々との交流を楽しみながら、眠っている何かを発見していくというキャッチボール方式で行われた。 ワークショップ形式で7つ程のプランが事前に設定され、参加者は自身の興味のあるワークショップに参加し、グループで調査、発表を行った。その中で、私は下血塚島という下浦地域にある無人島の一つに上陸し、そこでアートな出来事を発想するという「無人島アート化計画」というワークショップをメインに参加した。無人島上陸の様子や、無人島でのワークショップの様子を映像に残しつつ、そこから下浦地域の新しい発見を見いだせないかという考えから、下浦を映像を通して表現するという「下浦映像班」にも非力ながら所属する運びとなった。無人島へは、下浦から地域の方々に船を出していただき上陸するといった行程で、乗船中には、下血塚島の歴史や、地域の方々が島をどのように思っているのかといったお話を聞く良い機会にもなった。島へ上陸後は島の周辺を、足を使って周りながら発見をしつつ、アイディアをまとめていく形で調査が行われた。島の周りを歩き始めると、海岸線の砂浜にびっしりと敷き詰められているかのように貝殻があり、その上を歩くだけで参加者の足あとが良いリズムを作りちょっとした創作音楽を作る事が出来た。他にも波の音、森の音、風の音、人が生活していない場所だからこそ聞こえる音の存在はとても大きく、これを島の新たな資源として活用する事が出来ないか、そんな風に感じた。他のメンバーからも多くの意見が出てくる事になり、それらをまとめ一つの形にするといった作業に一番手間取った。発表の際には、それを思い通りに形にすることが出来なかったのが少し悔やまれるが、それほどまでに多くのアイディアが出たという結果には満足し、どうにかその中の幾つかを実際に形にすることで無人島をアートの拠点として活用したいと感じた。 今回の天草・下浦フィールドワークの主目的は、下浦地域の再生や新たな発見を通して再度活性化を試みるといった事であったが、個人的には、今回の参加を通して新たな視点や観点から考察する事を学んだように感じる。これまで学んできた、グローバリゼーションを通しての世界の変化に対して大きな枠組で物事を捉えるという考え方から、より細かい視点で身近に存在している出来事を感じとり、それを再発見する事で新たな可能性を見出す事が出来るというとても重要な事を得る事が出来た。無人島アート化計画でメンバーが出したアイディアをより具現化し、いつかは実現したいという気持ちも強くある。そして、もう一つのワークショップとして参加していた、無人島で撮影した映像も、編集し何かの形で下浦地域の新たな発見をする瞬間をとらえた映像という事で発信していきたいと考えている。 |
||||||||||||||||
| 五十嶋 さやか(いそじま さやか)/パワープレイス株式会社 | ||||||||||||||||
小学校のころから育った町に今も住んでいて、地元を離れるという気がさらさらない私が、ここで住んだら、きっと全く違った人生が送れるんだろうな、きれいな海ときれいな空とに囲まれて、きっとまったく違った目の色をして過ごせるんだろうな、と心の底から思いました。ほんと、きれいなところだと思いました。 初めてFWに参加させていただきましたが、最初は、「地域活性!なんて言っても、場所によってぜんぜん魅力が違うし、住んでいる人、旅に来る人、商売する人、それぞれが違う視点で考えていることだから、なかなかまとまるの難しいよなー」っなんて考えていましたが、今回みたいな動きでちょっとした風が吹くことで、それが心地よいと感じる人もいるし、風が強いなと思うひともいるし、だからやっぱりとってもまとまらないことなんだけど、でもあきらめずに続けるってことが、何かひとつ生むことにつながっていくんだろうな、だからまずはやってみる、そしてやめないようにしないといけないんだなって、しみじみと感じ直した3日間でした。それにしても、ほんときれいなところだと思いました。 |
||||||||||||||||
津高 守/JR九州 |
||||||||||||||||
藤原研究室の今年のフィールドワーク(以下「FW」と略記)はどうなるのだろうと思っていた初夏のある日、高倉さんから「今年は7月の第4週に下浦という天草石工の里でFWを行います」との連絡が・・・。「放送大学の単位認定試験の日じゃん・・・」と思っていたら、なんと6月初頭のレポートの締切りを失念して受験資格が無くなったため、何の支障も無くFWに参加できることとなってしまいました(笑)。 |
||||||||||||||||
| 倉内 慎介/パワープレイス | ||||||||||||||||
| 『シモウラ ヒート ハート ビート 』 | ||||||||||||||||
【シモウラ ヒート】 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
【シモウラ ヒートビート】 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
【シモウラ ビート】 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
【シモウラ ハート】 FW最終日、発表の場面で自分のやることは明快だった。それは従来、我が師匠であり、上司でもあり、天草の偉人でもある若杉大将がやることであった。 ①チームが一体となれるようShimoura Beatのポーズを考えた。 いよいよあの時の僕はデザイナーというよりは、アシスタントだった。 ④SHIMOURA BEATの音に合わせて変なダンスをする…。 これは考えてやったことじゃなくて自然と体が動いた。発表が終わった後、自然とチームでエンジンを組んで喜びを分かち合った。これこそ僕の求めていた盛り上がり。ライブだった。そして毎年僕のハートの一部を燃やしてくれるものだった。毎年得る物がある。だからまた来年もシモウラ ハートを燃やしにこようと思う。 最後に毎年、こんな素敵な機会を企画•提供していただいている藤原先生。実行いただいている九大の皆さま、受け入れてくださる天草の皆さまに感謝の気持ちを伝えたいと思う。 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||