 |
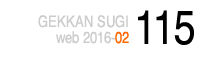 |
|
||||||||||||||||
| No,010 �u�щƂɉł���35�N�v | ||||||||||||||||
| ���E�ʐ^�^�@�������q | ||||||||||||||||
�ыƉƂɉł���35�N�B�ыƂ�“��”�̎����m��Ȃ��������B�ł���̖k���̎R�X�̕���Ɋ����Ƃ������͕s�v�c�Ȃ��̂������Ă������Ƃ��v���o���܂��B�����̎R�͂ǂ����Ă���Ȃɐ��R�Ƃ��Ĕ����������Ă���̂��낤���ƁB�ыƂɂ܂������������������́A�R�̖͂����Ăɐ����Ă�����̂��Ǝv���Ă����B�����悭�䂪�Ƃɗ����Ă������q�Ή��̏�������ɁA����Ƃ��q�˂��B�ǂ����Ėk���̎R�̖X�͂��ꂢ�ɐ��R�Ɛ����Ă����ł����A�ƁB�������킭�A�u���ꂪ���Ȃ��̒U�߂���̎d���Ȃ�ł���v�ƁB�����т�����ł����B��l�́A���܂�d���̎����ڂ����b���Ȃ��������A���̂���̎��͗ыƁ����ޏ����炢�̔F���ł�������B�p���������b�ł��B�n�����ܗ����Ă̏o�ŗ������т�����ł����B�����Ŏ�l�̎d�������ыƂ��������Ƃ����߂Ēm������ł��B���a55�N�A�щƂɉł������̂̉����m��Ȃ����́A��l����Ȗ�ȎR���c�ɂ�M�����p���ɁA���̐l�͎R�̐\���q�����m��Ȃ��A�Ǝv�����B���Ԃ�̎d���ɂ����̎g�����������A����Ă邱�ƁA�����Č�p�҂��c�邱�Ƃ̂ł���R�Â���ɖ��ƃ��}��������l�B�������͂ЂƂɂȂ����B �ł��A�ыƂ���芪������̗���͔N�X�������Ȃ�A�����c���ыƁA�R�Â���̖͍����n�܂����B���ꂩ��ь��O���[�v�̒��ԂƋ��ɁA�u��R�X�g�̎R�Â���ō����v�������悤�v�̊����������āA�ыƐ�i�n�̋g���l���̈��Q�ɂƎ��@���C���d�ˁA�V�����R�Â���ɒ���A���g�݁A�����Ɏ����Ă���B �@�c��A���Ă��炷���Ɏ}�ł���Ƃɓ���A��{��{�A�N2��̎}�ł���Ƃ͕��݂̂��Ƃł͂���܂���ł����B����ɂ��܂��đ�ςȂ̂́A�R�ւ̓����̘A���ł��B�䏊��a���鎄�Ƃ��Ă͋�s�����������Ȃ�����A���낢��킢�̘A���ł����B���ꂼ�ꂪ�E�ς̓��X�����������i���⎄���������ł��j�B�����āA��l�̌��ȁA�u�Ȃ�ł���ԂɂȂ��ƃ_���v�̐��_���K�����Ă��A����30ha�]��݂̂��ƂȐ��A�q�m�L�̐X�́A�����O����̎��@���C�n�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B���Ј�x�������k���ɂ����ł��������B����ȂɎ�̓����Ă���R�����邱�Ƃ��A�m���Ă���������Ǝv���܂��B �܂��Ɍp���͗͂Ȃ�B���݁A�ʒ��Ŗ��߂̖��C�ނ̊C�z�ۑ��ށA�����ۑ��A�i��ۑ��̉��H���肪���Ă��܂��B67�̐E�l�C���̎�l�́A�����̎肪���Ă�����{��{�̖��A�F�l�Ɋ��Ŏg���Ă��������邱�Ƃɑz�����͂��āA�������ٓ������āA���Ɏ}�ł��������āA�͂����ɓo��A�}�ł���Ƃɖ������Ă���܂��B�߂������A�䂪�Ƃ̖��C�ނ��A�����̐��A�V��A���ؓ��A�����ȂƂ���ɖ��؊ۑ��A���ύނƂ��āA�g���Ă��������邱�Ƃ�����Ă���܂��B�������Ō�p�҂��A���Ă��܂����B�����łɂ��S���ɂ͐Ԃ���B�u�R�ɐ����āA�n��Ɋ��͂��v�̎�l�̑z�����͂��܂��悤�ɁB |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ��<���키���E���݂�>�@�{�茧�E�������k�������ь��O���[�v�@ | ||||||||||||||||
| No,009 ���̖��́w�ڂ��Ȃ��N�x | ||||||||||||||||
| ���^�@���c���͂� | ||||||||||||||||
�@���{�́A���␢�E�����璍�ڂ���A��ڂ�����镶���卑�ł���B"���킢��"�ɑ�\�����t�@�b�V������@�×����p����Ă���a�H�ɉ����A�l�X�ȃA�����W�荞�H�����A�����͂܂��܂��i���������Đ��E���ɔg�y���Ă������Ƃ��낤�B �@����Ȓ��A�wJapanese cidder�x���w���{�̐��x�i�w�B�ꂽ���{�̍��Y�x�̊w�������I�j�ƒm��A���i���i�労�������̂��Q�N�O�I�ł���B24�N���ыƂɌg����Ă��Ȃ���A�������{�ŗL�̎��킾�ƁA�l���������Ȃ������B �@���߂Č��ߒ����āA���͂܂��܂����̖��͂ɖ������Ă��܂����B�����āA���������̊�����U��Ԃ�A���Ƃ̂Ȃ������苭�������鎖���o�����B �@���́A�������k�������ь��O���[�v�́@�ȑO�͒j���ь��ɕt�����閼�O�����̃O���[�v���������A12�N�O�A�R�тɓ]���鐙�̌��ʂ������Ɋ��p�ł��Ȃ����̂��A�Ǝ��g�؍H�����̒��ŁA�n���̐��ƃr�[�ʂ��g������i���w�ڂ��Ȃ��N�x�ƃl�[�~���O�A���i�����Ĕ���o�����B�@ �@���Ȃ��̐g�̎���ɂ͖̉�����E���G��������鎖���o������́A����܂����H |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ��<�����E���͂�>�@�������k�������ь��O���[�v��\ | ||||||||||||||||
| No,008 �u�R�Ɛ�Ŏv�����Ɓ@�v | ||||||||||||||||
| ���^�ʐ^ �㑺�m�� | ||||||||||||||||
�@�{�茧�̔������k���Ɉڂ�Z���8�N�ڂɂȂ�B���̊ԁA�n�n���A�A���t���A������A�����E�Ԕ��Ȃǂ̑��э�Ƃ��田�̔��o�܂ł̎R�d���A�k���̓��Y�i�ł�������Y�Y����Y�Ă��A�k���̐����g���Ẵ��O�n�E�X����A�܂��J�k�[�E�J���b�N�ł̐쉺����ē����郊�o�[�K�C�h�Ȃǂ̎d���������Ă�����Ă��ē��X���炵�Ă���B |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| �\���ł̃J���b�N�B | ||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| �E�i�M��߂�|�̓��̎d�|���i�|���|���Ƃ�����ł͌Ăт܂��j�ɃE�i�M�������Ă���l�q�B | ||||||||||||||||
| ��<�����ނ�E�悤�ւ�>�@��w���ƌ�@���s�̔��R���œc�ɕ�炵�̌��C��������B2008�N��B�ɖ߂�A�e�n�����������A�{�茧�������k���ɈڏZ�B�Y�Ă��A�R�d���A���O�n�E�X����A���o�[�K�C�h�Ȃǂ��d���Ƃ��Ȃ���A��˂₩�܂ǁA�܉E�q�啗�C�̂���Ƃŕ�炷�B | ||||||||||||||||
| No,007 �u�{�茧�E�܃����̐����g����20�N�@�v | ||||||||||||||||
| ���^�ʐ^ �]�䕔���� | ||||||||||||||||
�@�܃����ɋA���ė��āA���O�n�E�X���z���n�߂Ă���20�N�ȏ�ɂȂ�B |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
�Ă̊��������B |
||||||||||||||||
�@���̌�A�{��ɋA���ė��āu���O�H�[ EL CAMPO�v���n�߂��B��B�ɂ́A�����g���ă��O�n�E�X������Ђ�����������A�Z�p�����{�ɂ��킹�Đi���������̂�����A�������ɂȂ����B��͂�A���͓��{�̖�����C��ɍ����Ă���B100�N���ȏ�̕ď��Ō��Ă�ꂽ�Ƃ̊O�ǂ����J�ŕ����Ă���̂����邱�Ƃ����邪�A���Ƃ͈Ⴂ�@�ۂ��ʂ��Ă��Ȃ��悤�ɂڂ��ڂ��ɂȂ��Ă����B���{�̉Ƃ͕��y�ɍ��킹�Č����̂��A���J�ɓ��ĂȂ��H�v���K�v���B����̐�l�������悤�ɁB |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ��<�����ׁE����>�@���O�H�[EL CAMPO | ||||||||||||||||
| No,006 �u�����Y���ނ̏Z�܂��Â���Ǝq��ā@�v | ||||||||||||||||
| ���^�ʐ^ �ēc�u���q | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| �@�ߋ��A�c������Ɍg����l�̑��q����ĂĂ������ŁA�Z���Ǝq��Ă����X�Ƀ����N���Ă����̂ɋC�������B�Љ���ɂ����邠���邱�Ƃ��Z���̂Ȃ��ł��q���͊w��ł����̂��B�����Ĉ玩�B�������q�ǂ����炽������̂��Ƃ��w���Ă��炤�B�q��Ă�����e�̎p���́u�����v���ƁB�����ă^�C�~���O�����āu�⏕�v���邱�ƁB���ꂪ�q�ǂ��̐����𑣂� �����ɂȂ���B�ƌo������m�M���Ă������B�������Ȃ���V�тȂ���5������Ă�d�|�����ߍ��ؔT���̉ƁB�d�C���Ȃ�ׂ��g��Ȃ����R���̒��ŁA�R�R�����J���_�����₩�ɁA�L���Ɉ���Ăق����Ɗ肢�����߂�B�q�ǂ����ǂ����̂͐e�ɂ��S�n�悢�B�e�����̂��炩���ƂT���ւ̎h�����q�ǂ��Ƌ��ɖ�����Ăق����Ǝv���B | ||||||||||||||||
| �@���X�Ȃ��饥��ƕ����āA���̃C�}�R�R�A���Ȃ�����āH�ƋL�������ǂ��Ă݂��B �@�����������B���܂ꂽ�����琙��������Ԃ̑剹�ʂ��q��S�ɁA���̍���ɕ�܂�Ȃ���A���ۑ��̎R���Ƌ삯���A�t�H�[�N���t�g��O�֎Ԃ̃_���v�ɏ悹�Ă�����Ĉ���Ă����̂������B�{��H�������c���̑�H��q8�l�ƈꏏ�ɏZ��ł���������A���̍���Ƌ��ɑz���o���Ă���ƁA�����̉��ꂩ�炠�̍��̃��N���N����C��������݂������Ă���B�����傫���Ȃ�ƁA�c���╃�ƈꏏ�Ɍ������y��ɍs������A��Ǝc�ނŃp�`���R����������A����ē̌Z�����Ƀe�j�X�����ėV��ł�������襥��A�ō��Ɋy���������Ȃ��`�� |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ��<�����E���܂�>�@���v�Č����E�Z��X�܃f�U�C���v�� | ||||||||||||||||
| No.005�@�u�̍���܂��Â���v | ||||||||||||||||
| ���^���c���� | ||||||||||||||||
���̒n���ł���{�茧�����s�ł͌��݁A�w���ӂ𒆐S�ɋ�搮�����s���Ă���A��10�N�ȏ�o���܂����B���H�g�����ɔ����A�قƂ�ǂ̊����������ړ]�V�z�ƂȂ�A���ł͈ȑO�̖ʉe���v���o���Ȃ����A�X���݂��ς��܂����B�������i�ނɂ�V�����X�ɂȂ��Ă͂���̂ł����A�����Ȋ��z��"���ꂢ�ɂ͂Ȃ�����"�Ƃ������̂ł����B�ȑO�͗l�X�ȋƎ킪�e�X������F��`������Ă���A�ǂ������Ό��A�t�������ΊX���݂Ƃ��Ă̓o���o��…�B���݂͋�悲�Ƃ̎{��B����茈�߂�"����"������A�i�ϓI�ɓ��ꊴ�����܂�Ă���܂��B�������V���ނŌ`�����ꂽ�X���݂́A�ǂ��������₵���Ƃ������o������܂����B���͌��z�m��ɏ������Ă���A���z�m���"�i�σf�U�C���u�b�N"���Ă��悤�ƍl���܂����B |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
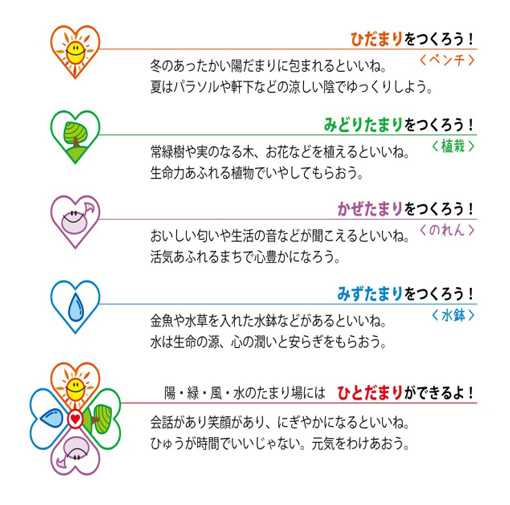 |
||||||||||||||||
| �u�b�N�����(�ꕔ) | ||||||||||||||||
| �������w���̍��A���Ƃ��V�z����܂����B���ł��o���Ă���̂����̓����ł��B���A����ɍs���Ƃ��܂ɐ̂̂��Ƃ��v���o���܂��B�c���Ƃ̒����A���т������撣�����\�t�g�{�[���A�킽���Ƃ̐�V�тȂ�…�B �͌܊��Ŏ���������ĂĂ���܂��B���ꂩ��̎q�������ɂ��������Ƃ������Ă��炦��悤�w�͂��Ă��������ł��B |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| ���Ў{�H�̖ؑ����w�Z�������Ԃ̊O���e���X����B(�S�Ēn������) | ||||||||||||||||
| ��<�Ђ炽�E���̂�>�@�g�����݊������ �����x�X | ||||||||||||||||
| No,004 �uKUMIKI�ɂ��āv | ||||||||||||||||
| ���^���� �� | ||||||||||||||||
���́A���܂ꂽ�{�茧�����̐��Y�ʓ��{�ꂾ�Ƃ��������A�����{�k�ЂŔ�Q����ꂽ�{�錧�̍ޖ؉����狳���Ă�������B ��������A���̗��O���c�k�БO�Ɛk�Ќ��2�x�K���@����B ���̎��g�݂��f���炵���̂́A�n���̐l�������グ���̂ł͂Ȃ��A�Q�n���̎�҂��k�Ђ̎��ɐ��܂ꂽ�Ȃ�����J�Ȃǂ̑厖�ȐS�̂����悤�����������Ȃ��Ƃ����v������A���O���c�ŏo���邱�Ƃ�͍����Đ��܂ꂽ�Ƃ������Ƃ��B�����ɂ́A���g�̎Љ�o���̒��Łu�����Ƃ������Ƃ͉��Ȃ̂��H�v�Ƃ����₢�����܂�A�l��Љ�̖��ɗ��������Ƃ��������ɂ��ǂ蒅�����Ƃ����w�i������B �uKUMIKI�v�́A��ɊԔ��ނ𗘗p���ĉ��H����郂�m�ł��邽�߁A�R����邱�Ƃɂ��Ȃ���B ����Ɏd���̖����Ȃ����y�n�Ŏp���ꂽ�Z�\������Ă������Ƃɂ��Ȃ���B ���̎��g�݂́A��Вn�����ɗ��܂点�Ă����̂͂��������Ȃ��Ǝv���B �������y�������R����邱�ƂɂȂ���B������Ă�����ˁI�@����ς���{�l�ɂ͖��������B�����v���킯�ł��B |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| ���Y�̐��ނł����Ă���uKUMIKI�v�́A�Ƌ�����邱�Ƃ��o�����uKUMIKI LIVING�v�ƌ��z�܂ł��邱�Ƃ��o�����uKUMIKI HOUSE�v��2��ށB | ||||||||||||||||
| ��<���˂܂�E��傤>�@������Ћ��یc�����X ��\����� | ||||||||||||||||
| No.003�@�u�ؑ��̉\���v | ||||||||||||||||
| ���^�����[�� | ||||||||||||||||
�傫�Ȏ{�݂�ؑ��Őv����@������Ă����B�@�����O�܂ł͑��Ԃ�K�v�Ƃ���{�݂́A��{�v�̒i�K��������Ȃ��S�����������͂q�b���Ōv���i�߂Ă������A�ŋ߂͂܂��@�u�ؑ��ŏo���Ȃ����v�@����������B�@���̂��ߕ��Ђł́A���̐��N�Ԃŗc�t���E�f�Ï��E����Ҏ{�݁E�W��{�݂ȂǁA���Ԃ�L����ؑ����z�̎��т����Ȃ葝���Ă����B�@�{�茧�ł����Y�ނ̗��p�ɗ͂����Ă��邪�A�����2010�N�Ɏ{�s���ꂽ�u�������z���؍ޗ��p���i�@�v�ɂ��A�������悵�Č������z���̖ؑ����𑣐i���Ă��闬��ŁA�S���I�ɂ��w�Z��ۈ珊�Ȃǂ̋���{�݂͂������A����܂ł��܂�ؑ��ł͌��z����Ȃ��������̂܂Ŗؑ����z�ɂ��铮�����i��ł���B�@ �o���邾���ؑ����z�Ƃ��������R�͂��������邪�A�ЂƂ͉��g����Ȃǂ̒n�����ی�ɍv���ł���Ƃ������ƁB�@�܂��A���Ȃǂ̒n���������g����Ƃ������ƁB�@����ɂ��n���Y�Ƃ����C�ɂȂ�Ƃ������ƁB�@�����Ă����ЂƂ̗��R���ؑ��̍ő�̖��͂��Ǝv�����A�ؑ���Ԃ��^����S�n�悳�͐l�Ԃ̌܊��ɖ�����^���Ă����A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���Ă���B�@ ���̓��{�̓`���I�ȑf�ނ��A���ܐV���ȑf�ނƂ��Ė��m�̉\�����߂Ă���B |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| ���Аv�̕����A�����s���̖؍މ��H�H��ł��B | ||||||||||||||||
| ��<����ǂ��E�Ђ��>�@�������q���z�v�������@�Ζ��@�@�ꋉ���z�m | ||||||||||||||||
| No,002 �u���̖��v | ||||||||||||||||
| �� / ���i�T�� | ||||||||||||||||
���ނ��g���ĉƋ�E�������点�Ă����������ɁA���q�l�ɂ悭�������t������B ����Ȏ����v���悤�ɂȂ����̂́A�ŋ߂̎����E�E�E�B �Ƃ̃f�U�C�������̕��͋C�A���C�t���[�N�A�������猚��E�Ƌ�̍ގ��E�`�E�F�����߂Ă����A���q�l�ƕG�������킹�č���Ă����B ���A���̑�햡���A��w�𑲋Ƃ��Č���p���ł��ꂽ���q�Ɩ�����Ă���B |
||||||||||||||||
| ��<�����Ȃ��E����>�@�L����Ж��i�Ƌ�@��\������@ | ||||||||||||||||
| NO.001�@�u������̃X�X���v | ||||||||||||||||
| �� / �y��T�q | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| �@���{�͑�H�����łȂ��A�����w���̐E�l�̋Z�p�����E��ł��邪�A����͊����i�ɉ�����A�e�������Ă���������p�Ƃ��Ă��܂��A����͐́A�בg�ŁA�e�q���ɓn���ĕt�������̂��閖�i�Ƌ��ɁA���˂̐��ō���Ă�������B �@���́A����Ȍ�����J���t�H���j�A������ɔ���Ȃ������ƍl���Ă���B �@�X�M�_�������o�[�̕��ŁA�A�o�ɋ������������琥��A�l���Ē����Ȃ����낤���B |
||||||||||||||||
| ��<�ǂ��E�䂤��>�@NPO�@�l�܃����여��l�b�g���[�N ������ |
||||||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||