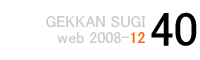|
連載 |
|
| |
いろいろな樹木とその利用/第5回 「タニウツギ」 |
文/ 岩井淳治 |
| |
杉だけではなく様々な樹木を紹介し、樹木と人との関わりを探るコラム |
| |
|
|
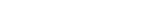 |
今年の5月下旬頃、ちょうどタニウツギが満開の時期に写真を撮りました。でもこんなにきれいなのにどういうわけか昔から縁起が悪いと言われ、家の中に持ち込んだり飾ったりしない花なんですね。どうしてでしょうか? その辺の話を主体にしていきたいと思います。
第5回目は「タニウツギ」です。 |
| |
|
| |
● |
| |
|
| |
 |
| |
道路際に咲くタニウツギ(H20.5.22.撮影) |
| |
|
| |
北海道、本州の主に日本海側の山地に生育するタニウツギは、痩せ地や湿性地にも成育する樹種で、2~3m程度の低木性木本です。道路際やなだれ斜面など明るいところを好む先駆種樹木です。5~6月頃漏斗状の薄桃色から紅色の花をつけます。
本州でも関東から東海にはタニウツギではなくハコネウツギ、ニシキウツギなどのタニウツギ属植物が分布していますが、日本海側のタニウツギほど民俗学的に利用されていないようです。
そんなタニウツギですが、どのように使われてきたのでしょうか。 |
| |
|
| |
●名前の由来 |
| |
漢字では「谷空木」と書きます。ウツギという意味は中が中空であるということで、髄が大きく木部が少ないことによります。正確には中空ではなく、髄として軟らかいスポンジ状のものが詰まっています。
タニウツギは方言の方が興味深い名前がついています。方言のいろいろは別途独立項目に記載しますが、ここでは代表的な方言の意味を考えていきたいと思います。 |
| |
|
| |
| 『ズクナシ』 |
役に立たない(木) |
| 『イワシバナ』 |
鰯が取れる頃に咲く |
『サオトメバナ』
『タウエバナ』
『アゼヌリバナ』 |
田植えの時期に咲くことから |
| 『カテノキ』 |
救荒の際に糧めしに入れ若葉を食べた |
『ダンジロウノキ』
『ダニノキ』 |
ダンジロウとは犬につくダニのことで、犬のダニは野山で騒いでいるときにこの木からもらうとされている。タニウツギについているアワフキムシをダニと間違えてのことらしい。 |
|
| |
|
| |
いろいろとありますが、農耕や漁などの生活に関連した名が多い反面、役に立たないというマイナスの意味もあります。その最たるものが『カジバナ』です。 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
子供の頃、花がきれいだから家に持って帰ってきたら、家の人に「縁起でもない」といわれて捨ててきたという思い出のある人もいることと思います。花はすごくきれいなのにどうしてそんなことを言われるのか非常に疑問だったので、いろいろ詳しい方に聞いておりましたところ養蚕と関係があるらしいことが分かってきました。
真相はタニウツギの花には蜂がついていることが多いらしく、その蜂が蚕の敵であるからのようです。それで、花を家に入れさせないために火事になるという話でインパクトを与えていたのでしょう。
もしくは本当に火事が起きたのかもしれません。また、木が「空木」なので軽く燃えやすいからという説も聞いたことがあります。
花はほんとにきれいなんですがねぇ・・・ |
| |
|
| |
|
| |
タニウツギの花 |
| |
|
| |
●その他の利用 |
| |
飢饉の際にかて飯にして増量したり、あんぼ(焼餅)の中身に入れたりと救荒植物として利用されていました。
その使い方の詳細が石川理紀之介氏の「山居成蹟」という書物に書かれています。「葉を採るには平年なれば山野へ出で、一日一駄くらいは易く柴とともに刈り得らるるものなり、之を内に持ち帰り葉をこきて其の儘干し臼にて細にすべし、但し米*(竹冠に麗)位のものにて通すべし、余り細ければ粉臭くして食しあしし、久しく貯え置くには暫時水に入れ蒸して干し上げ、二重俵に入れて火棚の上にをくときは幾十年も味かわらざるなり、又食するには干しあげたるを煮出して絞り、炊きたる飯の上にあてうらすべし、多分に煮たる時余りたるは水に入れて置、飯たく毎にしぼり交ゆべし」
一度も試したことがないのですが、こんどの春にやってみます。 |
| |
|
| |
●方言 |
| |
樹木を覚え始めたころは方言名などには興味がなかったのですが、今は、方言名こそ重要な情報が詰まっており、方言名を良く知ることが必要だと思っています。
ヤマウツギ、ウツギ、タウツギ、ミヤマガズミ、サオトメウツギ、サツマウツギ、エイザンウツギ、カンザシバ、カザ、ガサノキ、ガザ、ガサキ、ガジャ、ガサ、ガンジャシバ、ガンザノキ、カサノハ、ガンジャ、ガジャバベニウツギ、ベニザキウツギ、アカウツギ、ボタウツギ、ヘイナイウツギ、ドウダンウツギ、アカツゲ、ヘイナイ、ズクナシ、アカチョウジ、ケタノキ、ヒキダラ、ミヤマガマズミ、シイバナ、イワシバナ、イワスンバナ、ウノハナ、ドオッペ、カジバナ、タウエバナ、カテノキ、シャボングサ。
(上原敬二著 樹木大図説Ⅲ より引用。歴史的かなづかいは改めた。)
シャボングサはアワフキムシがついていることからでしょうが、やっぱり外来語のシャボンからなんでしょうか。 |
| |
|
| |
|
| |
【標準和名:タニウツギ 学名:Weigela hortensis(Sieb. et Zucc.) K.Koch(スイカズラ科タニウツギ属)】 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
●<いわい・じゅんじ> 某県にて林業普及指導員を務める。樹木の利用方法の歴史を調べるうち、民俗学の面白さに目覚め、最近は「植物(樹木)民俗学」の調査がライフワークになりつつある。
|
| |
|