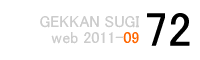|
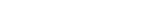 |
高浜フィルドワークに参加して |
| |
文/ 田中光徳 |
| |
|
| |
暑い日が続く7月16〜18日まで、とにかく熱く語りすぎて大変だったということしか思い出せない。 「スギダラのメンバーには色々な面白い連中がいるな。高浜にはこんな人たちはいない」と思った私だが、3日間ずっと参加するうちどんどん連中の話術にはまり、おとなしかった私もついつい熱く高浜の話を語り出してしまっていた。 |
| |
|
| |
「高浜には偉大な上田家7代庄屋宜珍さんがいた」という話をどんどんやってしまったわけだが、少しでも高浜の思いを伝え、初めて高浜に来た人達に強い印象を残してもらいたいと突っ張った様にも思える。 |
| |
 |
| |
文化庁登録有形文化財登録指定 上田家庄屋屋敷の庭にて |
| |
|
| |
そして最後の発表は結局7代目宜珍翁の紙芝居。それも面白い仕上がりに「これは次に繋がるな」と確信した高浜フィルドワークだった。今回は色々な方と話ができ大変楽しく思い出に残る3日間でありました。 |
| |
 |
| |
よしうず君の紙芝居で熱く語る田中さん |
| |
|
| |
●<たなか・みつのり> 上田家庄屋屋敷のボランティアガイド |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
高浜フィールドワークを終えて |
| |
文/田崎茂子 |
| |
|
| |
 |
|
七月の暑さにも負けない藤原先生御一行に、暑さはどこかに吹き飛んだ日々でした。
二日目の昼食でせんだご汁作りに参加しました。 時節柄唐芋の調達が出来ず、じゃが芋とかぼちゃのせんだご汁にしました。これはだごが黄金色に輝き、食欲を誘いました。
民泊でも、中国の留学生と熊本の院生さんでした。 何の勉強をされているのか興味がありましたが、中国の様子を聞いたり、中国からの日本の様子が聞けて、私の方が勉強になりました。日本の文化は中国、韓国が基になり、それぞれの国で独自の文化として生まれ変わり、その中で生きている事の不思議を思いました。 我が家にとっては、何度目かのホームステイですが、それぞれの人達との出会い、文化の違いを体験できて有意義さを感じています。
|
| 振舞われたおにぎりとセンダゴ汁 |
|
| |
|
|
|
| |
 |
| |
皆でセンダゴ汁をいただきました。おいしかった!(倉) |
| |
|
| |
苦言を呈するとすれば、高浜フィールドワークって何だったのか、つかめなかったのが残念でした。又、地元の方も聞いてみたいとの話も出ていました。昼食づくりとステイ先だった事だけが、印象に残ったものでした。 |
| |
|
| |
●<たさき・しげこ> |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
高浜の懐かしい未来へと向かう地図 |
| |
文/写真 中川みどり |
| |
|
| |
葡萄の棚と無花果の
熱きくゆりに島少女
牛ひきかよふ窓のそと、
『パアテルさんは何処にいる』 |
| |
|
| |
これは北原白秋の「ただ秘めよ」という詩の一節です。 彼や与謝野鉄幹を始めとする5人の文人たち、いわゆる「五足の靴」が旅した高浜。 それから100年の時を超えて、今度は素敵なアイディアとオヤジギャグ満載の愉快な面々が訪れてくれました。 |
| |
|
| |
「五足の靴」ゆかりの高浜ぶどうを量産し、それで薫濃き葡萄酒を作るー 熟年の高浜男児たちの、この祈りにも似た夢を現実へと近づけるべく、スギダラのみなさんや学生さんたちは有望かつ有効なアイディアを色々と出して下さいました。 |
| |
|
| |
まずはブドウによる景観づくり。 |
| |
|
| |
 |
| |
ブドウ棚のアーチやトンネルを配置して、白秋が詩に書いた光景を現代風に再現する。 |
| |
|
| |
酒を醸したはずのつもりがなぜかビネガーに変身!? それならば原料を既存の酒造メーカーに送り、商品の外注も有りなのでは? 思いつきそうで思いつかなかったアイディアを得て、高浜ブドウという地域の宝が磨きをかけられ輝きを増してきてはいるものの、今後不足が予想されるのは労力と継続力です。 高齢化と過疎化が進む地域ですので、今後も外部からのご支援をお願いしたいところです。 |
| |
|
| |
また、当地の観光資源としてどうしても挙げておかねばならないのは天草陶石と、それを原料にして生産されている白磁です。 これに杉やヒノキもプラスして、高浜オリジナルなプロダクツで町並みを彩っていこう! こんなふうにみなさんがより具体的に描いてくれた「高浜の懐かしい未来」が実現するのを私は夢みています。 なので次なる取り組みはそこに辿り着くための地図作りです!! |
| |
|
| |
 |
| |
|
| |
というわけで、スギダラの皆様今後もどうぞスギ長くよろジキお願いいたします(笑) |
| |
|
| |
●<なかがわ・みどり> (社) 天草宝島観光協会 |
| |
|