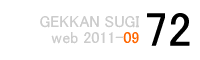|
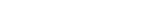 |
スギダラ北部九州・宮崎支部 |
| |
|
| |
懐かしくも羨ましい土地と仲間たち |
| |
文/ 辻 喜彦 |
| |
|
| |
【いざ、天草高浜へ】 |
| |
|
| |
スギダラのイベント時には、いつも「絶対に愉しい時間が待っているはず」「参加しないと後悔する」とモゾモゾし始め・・・迷わずにお邪魔してしまう。今回の藤原ゼミによる高浜フィールドワークもそうだった。天草高浜という地で3日間に亘り、濃くて暑く熱い時間が過ごせるはず・・・。藤原先生や学生さんはもちろん、高浜の方々とも面識が無かったが、スギダラメンバーが揃っていれば怖いものなし!である。絶対、熱くなるに決まっている・・・。 しかし、いざ熊本空港から高浜へ向うと予想外の距離があり、最後にトンネルを抜けて目に飛び込んできた海の青さは、高千穂・秋元集落にも山深さにも匹敵するほどで、外界から残された「別天地」へやってきてしまったと少々驚いた。 |
| |
|
| |
【高浜の町との出逢い】 |
| |
|
| |
到着が遅れたこともあり訳の分からぬまま、トランセクトウォークへと参加した。ボクは、元々大学卒業後、自然な流れで全国の歴史的町並みの保全と地区全体の生活環境整備(歴みち事業)にずっと携わってきた。そんな事もあって初めての町を歩くと、町の変遷の痕跡、路地や暮らし方などに目が入ってしまう悲しい習性が身に着いてしまっている。高浜は、というと、旧湊だった川筋から延々と築かれた石積で町割が形成され、とても清々しい水が流れ、山々が背景となった風景がそこにあった。とても暑かったが麦藁帽子のおかげもあり、風が心地良く、懐かしくも羨ましい土地に魅了されてしまった。若杉さんには怒られそうだが「こんな土地で生まれ育っていたら、人生大きく変わっていただろうな・・・」。そんな事を想いながら、高浜という土地に嵌っていった。 |
| |
|
| |
【プログラムD(グループワークでの立位置)】 |
| |
|
| |
元々のグループ分けでプログラムDに配属されていて、お宝探しの視点で町歩きをしていたことから、プログラムDを選択した。地元の方5名、学生4名、スギダラ+社会人4名という一見バランスが取れていそうで、かなり濃いメンバーが揃っていた。地域の新たな宝=高浜ブドウを地域のビジネスへいかに繋げられるか? そんな事がテーマだったが、上中さん、千代田さん、津高さんが予想通り、どんどんアイデアを出し暴走する。地元の皆さんのお話しも尽きない。学生さんたちは、オジさんたちの終わりなきお喋りに辟易としかけていた。 このようなグループワークでは、全員が参加できようにしなければならない。今春まで宮崎大学の社会人学生だった頃も、地元の人たちと一緒に作業するきっかけが作れない学生の背中を何度も押してきた。自然と自分の立位置が見えてきた。 |
| |
|
| |
暴走するオジさんたちは置いておき、学生さんが地元の方々に年間行事やブドウやイチジクの育て方をじっくり聞いてもらうように作業段取りした。せっかくのグループワークでオジさん達に振り回されず、学生さんと地元の方々の間で会話を深めてもらいたかった。 「高浜暦」を創るためには、受け継がれてきた風習とブドウ作り(モノ育て)で、高浜の時間の流れに合ったプログラムが組めるのでないかと考えた。普通、ブドウ作りには3年かかるという。年間を通じた様々な風習があり、それが3回繰り返されると高浜ブドウが実をつける。 この土地にあった、ゆっくりした時間の流れだと思った。まちづくりも慌てずに3年位かけてゆっくりと取組んで、少しづつ高浜ファンが集えれば良い。そんな想いをまとめたグループワークだった。他プログラムより地味だったが、次のプログラムへ繋げられる提案が出来たと思う。 |
| |
|
| |
【何と贅沢な夕陽】 |
| |
|
| |
第1日目の夜のワークショップは、疲れと旨い肴と酒で酩酊し、実はよく憶えていない。第2日目に地元の皆さんに町の周囲を案内して戴いた。烽火台から見た海の広さは素晴らしかった。しかし、それ以上に感動的だったのは、海に沈む夕陽の美しさだった。ゆっくりと色彩と光を変化させ水平線の彼方に沈む夕陽。子供の頃以来だろうか? 懇親会場へ戻りながら地元の方とお話した。 「毎日見ていると当たり前の風景なので、ついつい、その価値を忘れてしまう」 こういう時間や風景があることこそが、本当に贅沢なことなのだ。それを初めてではあるが一緒に過ごしている仲間と分かち合える。こんな時間を過ごせたことに感謝した。 |
| |
|
| |
【高浜と仲間たちへの想い】 |
| |
|
| |
夢のような3日間はあっという間に過ぎ、そのまま台風の中を宮崎へ向い、その後も出張続きで心も体もクタクタだった。そんな折、三浦さんからこの夏休みの宿題が届いた。風の便りでは既に藤原ゼミ+スギダラ北部九州では報告会ならぬ呑み会が開催されたという。「愉しかったんだろうなぁ参加したかったなぁ〜・・・」またまた顔出したがりムシがモゾモゾし始めている。 |
| |
|
| |
ボクが今、携わっているまちづくりでは、これまでのように単に道路や広場を計画・設計デザインして終わりではなく、そのプロセスから地域と関わり、出来上がってからも使いこなしてもらうような「仕組み」づくりがメインの仕事となりつつある。これは宮崎日向市で南雲さん、若杉さん、千代田さん、津高さんたちと出逢った頃から少しづつ価値観が変わってきたことであり、皆もそのことに気づいていて今日の諸処スギダラ活動に繋がっている。 |
| |
|
| |
"当たり前のことなのに、みんな忘れていた。見えないフリして通り過ごそうとしていた"
"立ち止まってみれば、そこには懐かしいゆっくりとした本来の時間と暮らしがある" |
| |
|
| |
まさに高浜で経験したことそのものである。 地に脚を着けて、ゆっくりとしたペースで高浜の素晴らしさを大切にしていければ良いと思う。そんな取組みにまた参加したいと思う。もっと皆さんと知り合いたいと思っている。 今回、この宝物のような時間と機会を与えてくださった藤原先生やゼミの皆さん、高浜の皆さんへ心より感謝を申し上げます。 次回も是非、お声がけくださいね!! 楽しみにしています! ありがとうございました! |
| |
|
| |
●<つじ・よしひこ> アトリエT-Plus建築・地域計画工房 日本全国スギダラケ倶楽部 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
高浜の印象 |
| |
文/溝口陽子 |
| |
|
| |
先日の高浜FWでは大変お世話になりました。 初めての訪問となった天草でしたが、まち歩きをして散策したり歴史を知ったり、高浜のみなさんと交流させていただいたりとほんとに濃密な体験をさせていただいたことに感謝しています。 短い滞在期間ではありましたが、わたくし、高浜のまちにすでに魅了されております。 吸い込まれそうなくらい透明度の高い美しい海、初めて来るのになんとなく懐かしい感じを受ける高浜の町並み、歴史的価値も高い木造建造物の数々、今後の成長が期待される高浜ぶどう、高浜の方々の鷹揚さ、古くから町の基幹産業であった磁器、などなど・・・。 高浜にはそんなお宝がごろごろと転がっている!という印象を受けました。 |
| |
|
| |
そして何よりも高浜を大切に思い、盛り上げていこうとがんばっておられるみなさんの熱い思いにぐっときました。そんなみなさんの思いに共振するように、なんだかおもしろそうなことが始まりそうだという予兆が高浜ではすでに渦巻いているような気がします。 月に2度開催されているという朝市は地域の方々の交流の場ともなっているようで、みなさんが楽しんでおられる様子が印象的でした。「楽しいから続けられる」というのはまちづくりにもきっと共通する要素だと思うので(スギダラでも然り)、まずはその基本に忠実に?盛り上がっていくことが重要かと思います。 そうしていくと、人は楽しいことには敏感だと思うので、今はノリがいまいちだという若い世代の方々もきっと黙っていられなくなり、一緒にまちづくりのプロセスも共有したいと思ってくれるのではないかと想像しています。 多くの人を巻き込んで大きなうねりとなっていきたいですね。 |
| |
|
| |
それから、これまで天草といえば天草四郎にイルカ、塩というイメージを持っていたのですが、ここにzikiが加わるべく、磁器と他素材とのコラボを通してもっともっと浸透させていけるといいなあと個人的には思いました。 またぜひお邪魔させていただきたいと思っていますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
| |
|
| |
追伸: |
| |
旅館でのお料理も2日目お昼のカレーも大変おいしゅうございました! 作ってくださったみなさま、本当にありがとうございました。 おいしいものがあるというのもまたぜひ訪れたいと思うリーピート要因としてかなり重要ですよね! |
| |
|
| |
●<みぞぐち・ようこ> 日本全国スギダラケ倶楽部 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
優しさと素朴なチカラ |
| |
文/ 崎田真央 |
| |
|
| |
私が高浜ワークショップに参加して感じたこと。 地域資源やプログラムから離れて、2つ書きたいと思います。 |
| |
|
| |
1つめ。麦藁帽子の効果、そして、それを準備して下さった地域の優しさ。 |
| |
|
| |
緊張しがちワークショップ初日、みんなで普段被らない大きな麦藁帽子を被ると、不思議と仲間意識が生まれました。そして、仮装大会みたいなワクワクした気持ちになっていく。大きなツバのお蔭で、お互いの距離が掴めず、すぐぶつかってしまう面白さ。麦藁帽子の意外な効果を知ることができました。 また、案内板に「各自、熱中症対策を!」と書くだけでなく、「てげあちいかい、こっちでも準備しちょくね」的に(宮崎弁ですみません)、さらりと参加者を気遣って下さる優しさを感じ、素敵だなと思いました。 |
| |
|
| |
2つめ。素朴なチカラ。 |
| |
|
| |
迷いましたが、個人的な感想を書かせて頂きます。私には海で亡くなった叔父がいます。海好きで独特な口調の人だったのですが、地域の方と話すなかで、その叔父に似た口調の方が居らっしゃることに気付きました。今まで、イベントやワークショップでそのような経験は無く、とても不思議で切ない感覚を覚えました。 そこに生きる人と外から来た人が触れ合うなかで、何かの拍子にそれぞれの人生や時間をふと感じるような空気が生まれることは、土地のチカラだと思います。うまく言えませんが、楽しいという気持ちの裏には、そういった底知れぬ、意図しない、素朴なチカラが隠れているのかもしれません。 今回、初めてお伺いした高浜。これから新しいことをする時、私が感じた優しさや素朴なチカラを失うことなく、みんなでワクワクできたら素晴らしいなと思います。 |
| |
|
| |
●<さきた・まお> 日本全国スギダラケ倶楽部 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
高浜フィールドワークに参加して |
| |
文/佐藤 薫 |
| |
|
| |
高浜から戻って2週間が経ちました。あの濃密な2日間は未だあとを引いていて、慌しい日常生活に戻った今でも、時折あの目の覚めるように美しい海、皆で汗をかきながら、ゆっくりと練り歩いた町並み、小さな発見をする度にはしゃいでいた麦藁帽子集団を思い浮かべ、暫し思考があの美しい高浜に飛んでゆきます。 |
| |
|
| |
自分はデザインや町づくりなどとは全く縁のない生活を送っている一般会社員で、「フィールドワーク」と聞いただけで「ハードルが高い」と気後れする小心者。勿論知識も経験もないので町を知るにあたって比較する対象もなければ、何を観るべきかという基本的なことすら分かっておりませんでした。ただ、スギダラ的勢いだけで参加させて頂いた次第で、傍観者で居てはならない、皆さんにきちんとついていかないと!という焦りだけがありました。 が、そんな頭でっかちな焦りは1日目であっという間に消え去りました。地元の方々が丁寧に説明を加えながら優しく寄り添って歩いて下さる、全く気負うことのない町の探索。あれやこれやと知識ばかりを仕入れることより、ゆっくりと時間をかけ、実際に自分の目で見て、聞いて、歩いて、感じること、それで充分でした。 2日目は天草陶石をテーマとした妄想Bチームでの活動。机の上では行き詰って悩んでいたのに、車に乗り込んでベストスポット周りを始めた途端、自然発露的に皆がZIKIZIKI言い出しました。美しい海岸が見えてくると更にアイデアが止まらない!ZIKIエネルギーと笑いが満ちた車中で新しいZIKZIKIプロダクトが次々と生まれるあの空気感は最高でした。フィールドワークとはこういうことなのか、と目から鱗が落ちる思いでした。そしてそんな空気を生んだのは高浜という町(と、チームZIKZIKIの仲間!)でした。 |
| |
|
| |
残念ながら3日目の発表には参加できませんでしたが、どのチームの発表も大変盛り上がった、と伺いました。写真も拝見しましたが、皆さん実にいい表情をされています。参加者は勿論ですが、地元の方達のたくさんの素敵な笑顔を見て、我々が一方的に押し付ける形になるのではなく地元の方々も一緒になってプロジェクトを創り上げ、楽しんでくださったのだということがわかり、大変嬉しく思いました。 遠くから来たよそ者が、たった2,3日滞在しただけで、自分達の町のことをお節介にも好き勝手言ってくる、それを丸ごと受け止めてくださる地元の皆さんの寛大さ、柔軟さ、そしてノリの良さ。それがこの土地の未来が明るいと思わせる全ての要になっている気がします。 |
| |
|
| |
そんな熱い地元の人たちが居て、陶石や美しい海といったお宝が散りばめられた高浜という場所があって、正しく導いてくださる藤原先生がいて、楽しむことが大好きなお節介なよそ者集団が交わったフィールドワークが面白くないわけがありません!最初の不安なんかすっかり吹き飛んでしまい、今は楽しかった思い出しかありません。 今後もこのような「楽しい」取り組みが継続的に行われ、「よそ者、若者、ばか者」も入り混じって!高浜地区がますます元気になることを心より願っています。 |
| |
|
| |
最後になりますが、高浜地区の皆様、藤原先生、事務局の皆様、参加された皆様に心より御礼を申し上げたいと思います。本当に有難うございました。 |
| |
|
| |
●<さとう・かおり> 日本全国スギダラケ倶楽部 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|