 |
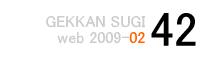 |
|
|||||||||||||||||||
春先に紫色の筒状花が咲き、桐畑ではなかなか見事な景観になります。生長が早いことでも知られ、女の子が生まれたら植え、嫁入り時に箪笥に作るとされていました。 |
|||||||||||||||||||
● |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
キリの大きな葉 (平成20年7月29日撮影) |
|||||||||||||||||||
日本の樹木のなかで一番大きな葉を付けることで知られるキリは、各地で栽培されており、会津や南部、越後などが産地として知られています。 |
|||||||||||||||||||
| ●てんぐす病(天狗巣病) | |||||||||||||||||||
てんぐす病という樹木の病気があります。よくサクラに見られ、症状としては枝が異常にふくらみそこから枝が叢生しほうき状を呈するもので、花が咲かず葉ばかり旺盛になってしまいます。花の時期に葉ばかりモジャモジャと生えるので見苦しいのですが、そういうサクラを見たことありませんか?ほうっておくと他の枝や木にも蔓延するので病気の部分を切って処分するしかありません。 |
|||||||||||||||||||
| ●キリの種 | |||||||||||||||||||
冒頭で書いたように、たまに都会の狭い土部分やアスファルトの隙間などの思わぬところから、にょきっと生えている(「ど根性桐」で検索)のですが、土砂を集めてビニール袋に詰めておいた袋からキリが生えて来て数ヶ月で1mほどに育っているのも見たことがあります。普通の樹木ではそんなところから生えてきませんし、そんなにすぐ大きくなりません。 |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
| キリの果実 | |||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||
| こんな種がぎっしり詰まっています | 翼の中央のケシ粒くらいの小さい種 | ||||||||||||||||||
| ●科が不定 | |||||||||||||||||||
手元の図鑑ではゴマノハグサ科と書いてあったり、ノウゼンカズラ科と書いてあったりし実際どの科に属するのかは本の著者の考え方で違うのですが、DNA分析すると、現在では独立のキリ科というものを想定したほうがしっくりいくようです。従来のどこかの科に当てはめるというのが土台無理だったようです。しかしここではゴマノハグサ科としておきます。 |
|||||||||||||||||||
| ●材の特性 | |||||||||||||||||||
キリにはいろんな特性があります。 |
|||||||||||||||||||
| (「改訂 新しい桐栽培の手引 全国桐材組合連合会等」から一部改) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| これらの特性から、箪笥、机、金庫の内箱、火鉢、天井板、建具、履物、楽器(琴、月琴、琵琶、太鼓胴)、舞楽面、能面、貴金属入れ箱、書類箱、掛け軸箱、木枕、器具柄、反物の巻き心・箱などに利用されてきました。 | |||||||||||||||||||
大切なもの、貴重品を入れる箱は桐でした。そういえば、へその緒を入れる箱も桐箱だったのですが、今もああいう箱に入れているのでしょうか? |
|||||||||||||||||||
| ●花の香り | |||||||||||||||||||
キリは春先にピンク色の花が咲き、直立した円錐花序を形成します。写真のように枝先に花をつけるので直接花の香りをかぐことは困難ですが、落ちている花をかぐと甘い香りがします。 |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
桐畑の開花状況 (平成20年5月12日撮影) |
|||||||||||||||||||
| ●そのほかの名称 | |||||||||||||||||||
キリノキ、ヒトハグサ、ヒトツバグサ、ハナギリ、ホンギリ、シトゥ、ジギリ、アバノキ。(上原敬二著 樹木大図説Ⅲより引用。) |
|||||||||||||||||||
| ●桐炭の利用 | |||||||||||||||||||
桐炭は絵画用木炭として使われますが、デッサン用などで使ったことがある方もおられるのではないでしょうか。(ヤナギ炭が多い) |
|||||||||||||||||||
【標準和名:キリ 学名:Paulownia tomentosa Steud.(ゴマノハグサ科キリ属)】 |
|||||||||||||||||||
| ●<いわい・じゅんじ> 某県にて林業普及指導員を務める。樹木の利用方法の歴史を調べるうち、民俗学の面白さに目覚め、最近は「植物(樹木)民俗学」の調査がライフワークになりつつある。 |
|||||||||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||