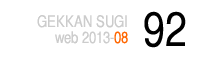|
特集 天草高浜フィールドワーク2013 |
|
| |
邂逅の力 〜私たちを、独白ではなく対話へ拓いてくれたフィールドワーク〜 |
文/
藤原惠洋 |
| |
|
|
| |
|
|
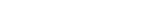 |
天草高浜のみなさま、
参加してくださったみなさま、
私たちをしっかりと見つめてくださったみなさまへ
2013年の夏もお世話になりました。お元気ですか。あらためて残暑お見舞い申し上げます。厳しい夏がまだまだ続きますが、どうぞご自愛ください。 |
| |
|
| |
さる7月13日(土)より7月15日(月・祝)の2泊3日、天草高浜地区全体を会場に開催しました〈2013高浜フィールドワーク+リデザインワークショップ〉ではたいへんお世話になりました。おかげで今年もまた個性豊かな多士済々の参加者が天草西海岸に集い、高齢化率43%にもおよぶ高浜地区の地域づくり課題を対象として、実践的な地域社会の再生デザイン提案を創造してワークショップを開催することができました。 |
| |
|
| |
もとより、この数年にわたる天草高浜へのフィールドワーカーとしての興味関心を超え、私にはある問題意識が大きく芽生えてきています。3年目ともなる今回の事業を各地の仲間達に呼びかける中、私はあえて次のような主旨をお伝えすることとしました。(「企画書」Ver10より抜粋)。 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
九州大学大学院芸術工学研究院藤原惠洋研究室は、毎日の暮らし空間や居場所を大切に守り残した地域社会を対象として、地域再生デザインに関する実証研究と実践的なデザイン提案活動を展開しています。今夏も、大学と地域社会の連携を基盤とした実践的デザインサーベイの合宿型学外演習を開催します。 |
| |
|
| |
厳しい格差社会の現実や限界集落の桎梏(しっこく)を乗り超えた地域社会には、必ず独特の人間力や紐帯力が随所に隠されています。そこに潜む魅力や資源を再発見し、人間力や紐帯力のひそみに触れながら、暮らすことや生きること、お互いを支え合うこと、といたって当たり前のことを見事にマネジメントし続けている地域社会から学びとることは少なくありません。 |
| |
|
| |
今回のフィールドは一昨年、昨年に引き続き、熊本県天草市の東シナ海を望む麗しい西海岸で知られる高浜地域を設定しています。高浜に潜む地域固有資源、暮らしの不便さや地域社会の不活性問題等を再発見し、その課題を丁寧に見つめ、解決への方策や隠された可能性のリデザイン(課題解決型提案デザイン)を行います。 |
| |
|
| |
既に3度目の継続開催となる今年は、これまで私たちが試みて来た活動が、どのような効果を生み出すのかを真摯に振り返り、これからの可能性を参加者全員で見極めたいと考えています。次世代型のデザイン活動やソーシャル・インクルーシブ(社会包摂型)な創造活動に関わりたいと志願する方々へおすすめの滞在型プログラムとなっています。積極的な活動を期待します。 |
| |
|
| |
そして、決して高浜での滞在や逗留を単なる物見遊山で終わらせること無く、そしてせっかくの異能・才能・超能力の持ち主たちを招き入れることなら、その達人パワーを瞬間芸のように発揮していただきたい、と事業の目的とフレームワークに腐心しました。その結果、昨年までのものをメジャーチェンジするかたちで次なるグループテーマを用意し、参加者を挑発することとしたのです。 |
| |
|
| |
|
| |
●目的 |
| |
| 1 |
天草市天草町の高浜地区における顕在・潜在した地域固有資源を「文化資源」として位置づけ直し、デザインサーベイ手法を援用しながらフィールドワークを通し再発掘していく。 |
| 2 |
さらには既存の文化資源としての上田家、天草陶器、町並み、高浜葡萄(ぶどう)、白鶴浜(しらつるはま)、地元産材杉の再評価と地域空間に潜在している課題や問題点に対して、解決型のリデザイン提案を行う。 |
| 3 |
参加学生にとっては、リアルな地域社会の課題発見と解決策探究・提案をプロのデザイナーを始めとする高度職業人たちと交流しながら体験的・実践的なキャリア教育の一環として位置づける。 |
| 4 |
参加するプロのデザイナーを始めとする社会人・高度職業人たちにとっては、実践的な社会の文化資源の再発掘や再評価に関与することを通し、九州大学大学院芸術工学研究院における社会連携プログラムへの関与を通したキャリア教育への貢献、さらには地域社会貢献や社会還元の一環として位置づけることができる。 |
|
| |
|
| |
|
| |
●グループテーマ |
| |
プログラムA
えこみゅぜ!国指定登録有形文化財上田家を活用、エコミュージアムコア博物館構想 |
| 上田家の役宅は築二百年近い歴史と伝統を有し国指定登録有形文化財に指定されており、これらを生かした高浜エコミュージアム構想とサテライト・コア博物館化を構想する。 |
|
| |
プログラムB
たかはまグッズ!天草陶石・地域固有資源を活用「タカハマたいせつプロダクト」構想 |
| 我が国最大の算出を誇る天草陶石を再評価しながらデザインによる付加価値かと高浜ブランド化を構想する。 |
|
| |
プログラムC
たかはまパーク!まちなか再生計画構想と旧役場跡地まちづくり交流広場構想 |
| 高浜地区の要とも言える旧役場跡地は現在、毎月第一第三日曜日の早朝持ち寄り朝市に用いられており、将来的にここをまちづくり交流広場として整備していくための提案を構想する。 |
|
| |
プログラムD
たかはまSOHO!ICTを用いたタカハマSOHOライフスタイルの提案 |
| 都市と地域の社会格差はいよいよ広がるが、こうした問題を改善していくために地域社会から創造的な生き方や暮らし方を実践提案していく。情報過疎とも言える地域社会に適切なICT環境を整備しモデル事業を構想する。 |
|
| |
プログラムE
よみがえり葡萄!高浜葡萄のよみがえりプロデュース支援とパーゴラ(葡萄棚)の試作 |
| 現在進展中の高浜葡萄のよみがえりプロデュース事業に参加し活動を支援する。同時に、インテリアデザイナー千代田健一氏による基本設計をもとに高浜界隈に展開していくまちなみパーゴラの試作を行う。 |
|
| |
プログラムF
たかはま編集局!高浜フィールドワーク+リデザインワークショップの記録と情報化 |
| 以上の活動を取材しつつ、高浜フィールドワーク+リデザインワークショップの意義と効果を間接的に評価していく。三日間「ふぃるどわくわく新聞」を発行し、高浜地区住民全戸配布を通して、活動の情報化を試みる。 |
|
| |
プログラムG
たかはまっ子!こどもたちとフィールドワーク+ドリームデザインワークショップ |
| 高浜の子ども達を仲間にしながら、面白フィールドワーク+ドリームデザインワークショップを行っていく。子どもたちの視点から高浜の遊び環境を見つめ直し、課題や問題を子ども達とともに解決して行く。 |
|
| |
プログラムH
たかはま海の幸体験ワークショップ |
| 高浜の西海岸の景観や海の幸を体験的に味わいながら、高浜の海の幸資源の魅力を探索していく。今後の漁業の6次産業化や海浜景観の視点から高浜の海の幸資源を見つめ直し、課題や問題を解決して行く。 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
夏らしい入道雲や強い日射しのもと、天候にも恵まれ夕陽もたっぷりと味わうことができる西海岸の豊かな海岸景観に包まれ、60名にも及ぶ遠来の参加者と快く迎え入れてくださった高浜住民有志のみなさんは、このような8つのテーマグループに分かれてフィールドワークとワークショップの活動を展開しました。 |
| |
|
| |
前段では高浜地区の随所に眠る地域固有資源の発掘作業に汗を流し、浮き彫りになってきた課題や問題に対しては叡智たっぷりのユニークかつ実践的なアイデアで大逆転していこうと有意義な地域再生デザイン提案の創出と発表に及びました。 |
| |
|
| |
また参加者中、20名にも及ぶ大学生諸君は、高浜地区のみなさまのご理解とご協力により、有志ご家庭に民泊させていただくという素晴らしい人生の体験をすることができました。海外からの留学生も多く、彼ら彼女らにとっては日本留学の忘れられない思い出になるに違いありません。受け入れご家庭のみなさまには、心より感謝申し上げます。 |
| |
|
| |
そしてさらに、2泊3日のスケジュールの折り返し、中日の14日(日)夕刻には高浜漁港を会場に、「夢高まる浜夕陽コンサート」と私たちが勝手に名付けた懇親交流宴を元気よく開催することができました。 |
| |
そこには、地元を代表する創作ハイヤ踊りで知られる舞踊集団丸尾會より音楽舞踊ユニット「ミニ丸尾會」とユニークな絶叫バンド「鎮」が参加してくれました。若さ一杯のパフォーマンスで気勢をあげ、さらには、その豊かな音楽性を堂々と訴えかける天草オリジナル音楽集団「音楽商店」の素晴らしい演奏と歌唱に会場は一気に盛り上がりました。 |
| |
そして参加者の中からも、河浦町出身の実力派デザイナー若杉浩一氏のソロギターぶりに一同感極まりました!また、ほのぼの楽器アンデス25を操る福田裕美さんの演奏ぶりも拍手喝采、とりは若かりしギタリスト九大生の福居君がつとめてくれました。 |
| |
|
| |
藤原惠洋研究室のこれまでの高浜研究を生かすべく用意されたグループワークのテーマには、高浜の地域固有資源に肉迫し楽しいアクティビティから洞察力溢れるフィールドワークまで、小学生たちから78歳の川口末枝さんまでの幅広い年代の地域住民の方々のご協力を得ながら、おおいに充実して展開しました。 |
| |
|
| |
最終日の発表会の成果は、こうした活動を通して見えてくる課題や将来への可能性を検討した上での見事な提案続出でした。活況盛況愛嬌御礼!!参加された誰もが、こうした意義を感じとられたことと思います。 |
| |
|
| |
また、たとえ高浜や会場となった高浜地区コミュニティセンターに来ることができなくても、こうした取り組みの多くは、会場から全国各地へ向け、インターネット通信によるUストリームを用いてライブ発信されていきました。そして、以上の活動の多くを成果づけ振り返ろうと、インターネット上の九州大学大学院芸術工学研究院藤原惠洋研究室「ふ印ブログ」には、数多くの写真による速報が発信されていきました。 |
| |
|
| |
さて地元高浜のかたがたには、まちなかでたいへんお世話になりましたが、みなさまは、このような私たちの活動に対して、何を想い、何を刺激され、何を考えられたことでしょうか。なかなかゆっくりとお話を交わす機会がなかったのが、ひとえに残念でしたが、次なる機会がありましたら、ぜひ生の声を聞かせていただければ幸いです。 |
| |
|
| |
そして、この3年間、いろいろな側面からご支援いただきました高浜地区振興会のみなさまに御礼を申し上げます。今後も高浜地域の誰もが参加しあって汗を流し笑顔を交わしあえるような地域づくりが進むことを願ってやみません。誰もが幸福になるような地域づくりをぜひ推進していただくよう、心より祈念しております。 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
さて今後の「よそもの」「わかもの」「ばかもの」の私たちの活動ですが、これらの成果は、今冬の良き日を選び、福岡市の九州大学を会場として「地域固有資源フィールドワーク+地域再生デザインワークショップ・シンポジウム」(仮称)の場を設けて行く予定です。 |
| |
|
| |
また日本文化政策学会研究発表大会(11月末、東京・青山学院大学)においても、疲弊する地域社会の再生契機をいったいどのように創出していくべきなのか、こうした観点からの研究成果を発表する予定です。こうした際には、あらためて高浜地区の皆様にもお伝えいたします。 |
| |
|
| |
また高浜地区のみなさまが、これまでの壮大なフィールドワーク+リデザインワークショップの成果を高浜地区の中で一人でも多くの住民の方々とともにもう一度見てみたい、と希望されるのでしたら、どうぞ天草支所もしくは高浜地区振興会の関係の方々にそうした意向をお伝えされてはどうでしょうか? お声をかけてくださる場合には、高浜地区での成果発表会を催すことも可能だと思います。 |
| |
|
| |
このようにみなさまとの不思議な邂逅を振り返りながら、私たちを、独白ではなく、対話へ拓いてくださったことに、あらためて心から感謝申し上げます。みなさまとの邂逅のおかげで、私たちは未踏の地を歩くこと(フィールドワーク)の醍醐味をたっぷりと味わうことができました。そして、みなさまとの対話を生かしながら、地域再生へ供することができるならとの真摯な思いから数多くのデザイン提案を行うことができました。荒唐無稽のものから明日にでも起業化できるような優れたアイデアまで多士済々な成果が、私たちの両手だけで足りず、みなさまと手をあわせつなぎ合わせてようやく持てる程に満載となりました。また、ささやかなホームステイではありましたが、学生諸君にとっては、きっと心に残る人生の1ページとなりうるものであったと確信します。こうした邂逅は必ずお互いを高め合う力となります。高浜に対して、私たちが感じとった言葉を最後にお贈りしながら、次なる邂逅のひとときを待つこととします。 |
| |
|
| |
もう一度会いましょう、夢高まる浜のみなさまへ。 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
このワークショップの3年間の活動は過去の月刊杉にも特集されています。参照下さい。
月刊杉72号特集(2011年9月号)「天草・高浜フィールドワーク2011開催」
月刊杉82号特集(2012年9月号)「天草高浜フィールドワーク2012」 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
ふ印ラボ(九州大学大学院 藤原惠洋研究室)ブログでも詳しく写真付でレポートされています。こちらも是非ご覧ください。
(写真下のタイトルをクリックすると、リンク先が表示されます。) |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
●<ふじはら・けいよう> 2013高浜フィールドワーク+リデザインワークショップ プロデューサー
工学博士・建築史家・まちづくりオルガナイザー・九州大学大学院芸術工学研究院教授・日本全国スギダラ倶楽部北部九州会員
九州大学研究者情報 HP: http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K002281/index.html
E-mail: keiyo@design.kyushu-u.ac.jp
藤原惠洋研究室: http://www.design.kyushu-u.ac.jp/~keiyolab/
ブログ: http://keiyo-labo.dreamlog.jp/ |
| |
|