 |
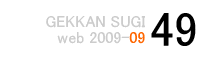 |
|
|||||||||||||
| 美しく豊かな自然に恵まれた「秦野」は、三方が山や丘に囲まれ、北には神奈川の屋根と呼ばれる丹沢連峰が連なり、南には渋沢丘陵と呼ばれる台地が東西に走っています。 そして、雄大な丹沢のふところの山々から流れでる川は清く豊かです。 |
|||||||||||||
| このような地形の特徴から「名水の里」として親しまれ、また、今から40年ほど前まで、日本三大葉たばことして名を馳せた秦野葉の生産地として知られていました。 たばこ栽培に欠かせない資源として、クヌギやコナラの落葉を苗床の肥料に、また、幹や枝は乾燥用の燃料(薪)に活用し、里山の原風景を保ちながら、伝統的な農村文化として自然界との調和を図ってきました。秦野の産業と暮らしが、里山の管理を通じて、湧水と牧歌的な景観を支えてきていました。 |
|||||||||||||
| しかし、たばこの生産拠点が移転してからは、里山の利用が減少し、秦野らしさが減少していきました。もう一度、秦野らしさ、秦野盆地の特徴を活かしたくらしと文化を取り戻したいというのが秦野市の考え方です。 | |||||||||||||
| そのような背景から、2004年に国県市住民が協働して、里地里山の保全再生活動が始まりました。2007年には、本コンテスト会場となった「表丹沢野外活動センター」が開設され、2010年には、全国植樹祭が秦野市等で開催される予定です。 | |||||||||||||
| このような背景から『表丹沢・間伐材等活用デザインコンテスト』が開催しました。 「はだの ぬくもりを感じるデザイン」をサブタイトルに、人工林や里山の手入れをして得られる間伐材を利用して、木のぬくもりを感じ、森や里地里山に親しむことにつながる作品を募集しました。 遊ぶ、休む、風景を楽しむ、道具を収納するなど実際に秦野盆地で活用できる作品の募集です。 |
|||||||||||||
| 2009年4月30日に締め切った第一次審査では、応募のあった600弱の作品の中から16作品が入賞しました。入賞した作品は、8月21日開催された第二次審査会において、以下の7点が受賞しました。 | |||||||||||||
| ●●●最優秀賞 [里山デザイン部門] 作品: 『竹ちぐら』 作者: 高橋慎一郎 (土の空間工房Sobato/東京都杉並区) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●●●最優秀賞 [里山活用部門] 作品: 『街を見下ろす丘で』 作者: CUT (代表者 和田彦丸/千葉県船橋市) |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●●優秀賞 [記念品部門] 作品: 『ジャムベラ』 作者: 佐野正明・智子 (愛知県名古屋) |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| ●●優秀賞 [小中学校部門] 作品: 『木のはちかざり』 作者: 石井瑞稀 (秦野市立東中学校) |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| ●特別賞 作品: 『Bamboo Wind Cage』 作者: 鈴木栄史 (音楽家・民族楽器演奏・作曲/千葉県一宮町) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●特別賞 作品: 『マルタフェンス』 作者: 北野和男 (神奈川県藤沢市) |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| ●特別賞 作品: 『マルタンじいさん』 作者: 長嶋海斗 (秦野市立鶴巻小学校) |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| ●以下惜しくも選外となりましたが、里山部門に於いて現地製作をされた力作を紹介します。 | |||||||||||||
| 作品: 『竹取物語』 作者:CUT(Chiba University Team)代表者 和田彦丸 千葉県我孫子市 チーム員:牛島隆敬、渡辺剛士、生出健太、奥村真倫子、郡司圭 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| 作品: 『するー(through)』 作者: 小山和則(千葉県我孫子市) |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| 作品: 『間伐材によるジャングルジム』など女子大生と共につくる楽しい制作 作者: 榎本文夫+駒沢女子大学人文学部空間造形学科 榎本ゼミ(東京都稲城市) 参加者:伊藤結、上田彩香、内海実季子、大澤明日香、齋藤恵里子、中野彩子、樋口祐麻 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| 講評・詳細については、審査員の南雲勝志氏+若杉浩一氏の審査統括をご覧ください。また最終選考に残ったすべての作品は「はだの里地里山」のホームページで見ることが出来ます。 | |||||||||||||
| 入賞しなかった作品の中にも、数多くのすばらしい提案がありました。 今回のコンテストを通じて、間伐材の活用、森林、里地里山の再生に関して、さまざまなデザインと勇気をいただくことができました。応募していただいたすべての方に感謝を申し上げます。今後とも、秦野盆地での取り組み、全国の里地里山、森林整備、間伐材の促進にお力添えをいただけますよう審査委を代表して御礼申し上げます。 |
|||||||||||||
 |
 |
||||||||||||
| 第二次審査会で、作者自ら作品のプレゼンを行う | 審査員による議論 | ||||||||||||
 |
|||||||||||||
| 主催者、審査員、応募者、それぞれが秦野の未来を考える会となった | |||||||||||||
●<たけだ・じゅんいち>コンテスト企画・審査員/東京農業大学学術研究員/里地ネットワーク事務局長/山村再生支援センター事務局長
|
|||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||