 |
連載 |
|
| |
杉という木材の建築構造への技術利用/第15回 「『ともいきの杉』 性能把握試験」 |
文/写真 田原 賢 |
| |
「杉の可能性を引き出す」木造建築の構造を、実例をもとに紹介していきます |
| |
|
|
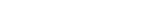 |
*第13回 「京都府美山町の杉の性能把握実験・その1」は こちらへ |
| |
*第14回 「京都府美山町の杉の性能把握実験・その2」は こちらへ |
| |
|
| |
『ともいきの杉』 性能把握試験 |
| |
|
| |
前号では2004年5月17日京都府林業試験場(和知町)で、非破壊検査でヤング係数の測定を実施し、特に見た目が悪いとされるような材は一般ではまったく市場価値がないとされる材を選木した結果、3/4以上は普通の建築用材として問題ないことがわかった。 |
| |
但し試験装置の許容範囲を 越えた含水率の材については、測定値の信頼性が低いので、引き続きの検証として2004年7月14日に近畿職業能力開発大学校で、ヤング係数の破壊検査を実施した。 |
| |
その実験結果について下記に示す。 |
| |
|
| |
|
非破壊検査
叩いている木口の反対側の木口に設置された集音機で集音し、波長を分析する事でヤング 係数を求めます。 |
| 短所:含水率によっては測定されたヤング係数の精度は低い。 |
長所:破壊されないので、商品として使用可能。 |
|
 |
|
破壊検査
2点で支持された試験体の材長を3等分した2点で載荷し破壊するまでの鉛直方向の変形量 と荷重量を計測します。 |
| 短所:試験後は、材が破壊されているので商品として使用不可能。 |
| 長所:含水率の高・低によらず、100%正しいヤング係数が算出される。 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
検査別のヤング係数値比較 |
| |
|
| |
結果を先に述べますと、非破壊検査結果と破壊検査でのヤング係数値に平均的には大きな差異はなく、非破壊検査でのヤング係数の値につい ても信頼性が高いことが証明された。 |
| |
また、破壊検査は非破壊検査に比べて(時間がかかるので)試験体数が少ないですが、ヤング係数の出現率は大差ないことが確認された。 |
| |
|
| |
|
| |
【出現率】 |
| |
ヤング係数等級 |
E50 |
E70 |
E90 |
E110 |
E130 |
試験体数 |
非破壊検査 |
13% |
48% |
33% |
6% |
0% |
67本 |
破壊検査 |
16% |
50% |
21% |
8% |
4% |
20本 |
|
| |
|
| |
|
| |
【比較表】 |
| |
No. |
巾 |
成 |
非破壊検査 |
破壊検査 |
誤差 |
[mm] |
[mm] |
E [N/mm] |
基準E [N/mm] |
% |
1 |
125 |
273 |
7360 |
6735 |
-9 |
2 |
123 |
246 |
9153 |
8389 |
-9 |
3 |
124 |
275 |
6831 |
6077 |
-11 |
4 |
125 |
214 |
5723 |
6725 |
15 |
5 |
125 |
187 |
7546 |
8484 |
11 |
6 |
127 |
188 |
11466 |
12334 |
7 |
7 |
125 |
192 |
10486 |
10075 |
-4 |
8 |
128 |
189 |
6762 |
6079 |
-11 |
9 |
126 |
189 |
9379 |
8895 |
-5 |
10 |
88 |
88 |
5586 |
5773 |
3 |
11 |
95 |
96 |
6066 |
6287 |
4 |
12 |
93 |
93 |
6115 |
6725 |
9 |
13 |
104 |
105 |
8124 |
7550 |
-8 |
14 |
121 |
121 |
10016 |
9890 |
-1 |
15 |
120 |
120 |
5713 |
6249 |
9 |
16 |
124 |
123 |
8124 |
8430 |
4 |
17 |
120 |
124 |
6811 |
6034 |
-13 |
18 |
121 |
121 |
8722 |
8763 |
0 |
|
| |
※破壊検査のヤング係数に比べて非破壊検査の値が高いと危険側の誤差として「−」で表示される。 |
| |
|
| |
|
| |
特にその値が大きいに材(≒15%)には材下端に「死節」等の欠陥が有り、その為に破壊検査のヤング係数が低くなることは予想していたが、その予想通りであった事が確認された。 |
| |
この事から、欠陥がある様な劣化構造材や若齢材であったとしても「使う側で工夫」すれば、十分に構造材として使える事が理解できる。 |
| |
問題は、こう行った事を建築士や工務店、また大工等の使う側が理解できなければ、「問題が起きない様に強度の高い集成材か、米松で行こう」となるので、杉の使い方を川下側で工夫する必要がある。 |
| |
当方はこれからも「杉を生かす構造設計」を続けていくつもりで有る。 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn
|
| |
|

